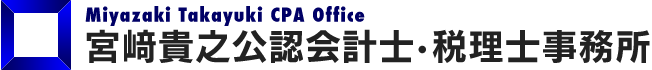【会計】一括償却資産の少し踏み込んだ処理を考える(難易度:少し細かい)
2016年05月21日一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得し、それを取得したときから3年間にわたり均等償却する際に使用する勘定科目です。
この3年間にわたり均等償却していく方法は、税務上も会計上も認められている方法です。ふつうに36か月で月割り償却してもよいし、また、期中に取得した場合、月割りせず最初の期に1年分償却してもよいです。
今回は、その一括償却資産の少し踏み込んだ話をします。
最近、経理の方から、①「当社は表示上、間接法だが、3年経って償却し終わったら残存価額はゼロなので、帳簿から科目を消してもよいか?」とか、②「当社は、表示上、直接法だが、一括償却資産は減価償却累計額の注記に含めるの?」などの質問が、たまたま重なりました。
まず、直接法(直接控除方式)、間接法(間接控除方式)とは減価償却資産の貸借対照表における表示方法をいいます。ここではかんたんに、ここまで。
①の質問は、間接法なので貸借対照表に「資産×××(減価償却累計額×××)」と残ってしまうのでどうしたら良いか?消したいな、、ということ。
②の質問は、通常、減価償却累計額は直接法の場合、決算書に注記するのですが、これに一括償却資産の償却累計額も含めるんだっけ?ということです。
意外にこの質問ありますし、いわれると「そうね・・」と素朴な疑問かも知れません。
<検討>
少し専門的になります。
一括償却資産を除却した場合、その取扱いは、除却が生じたとしても、あくまで税務上、一括償却資産の損金算入限度額までしか、損金算入できません。
つまり、3年間で均等償却することにしたので、1年後に除却して手元に無くなったとしても、その後残りの期間を償却し続けるのがルールです。(これは除却だけでなく、全部または一部の譲渡のときでも同様のルールです。法人税基本通達7-1-13)
また、地方税である固定資産税の計算においても、一括償却資産は、そうと決めたら課税対象から外れます。
このような点から、一括償却資産は、減価償却資産の中でも独自のルールを展開しているもの、他の減価償却資産とは異なる取り扱いをするもの、といえます。
<結論>
よって、一括償却資産については、
①「当社は表示上、間接法だが、3年経って償却し終わったら残存価額はゼロなので、帳簿から科目を消してもよいか?」という点。
仮に直接法を用いた場合、3年後には貸借対照表から無くなっている(元帳上からもゼロとなり無くなっている)ため、これと同様に考えて、間接法を用いた場合にも3年後には振替仕訳(※1)で消してしまっても良いでしょう。
(※1)仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
| 減価償却累計額 | ××× | 資産 | ××× |
また、②「当社は、表示上、直接法だが、一括償却資産は減価償却累計額の注記に含めるの?」という点。
注記の減価償却累計額に、一括償却資産の償却額を含める必要はありません。
減価償却累計額に含めるのは、固定資産台帳に計上している資産で、かつ法定耐用年数で減価償却しているものだけでよいからです。
一括償却資産は独自のルール展開をしていますので、これには当たりません。
以上、一括償却資産はそうと決められたときから、独自ルールに沿って処理されます。手元に無くなっても3年均等償却し続け、また逆に、3年後に償却し終わった場合は手元にあっても、帳簿から思い切って消してしまってよい(※2)と思います。
それでは。
(※2)手元にある場合は、資産管理はしましょう。台帳に備忘録で残すとか、番号管理するなど。
(注)難易度
「やさしい < ふつう < 少し細かい」
難易度は、経理初心者~若手経理ご担当者の方くらいを目安にしています。